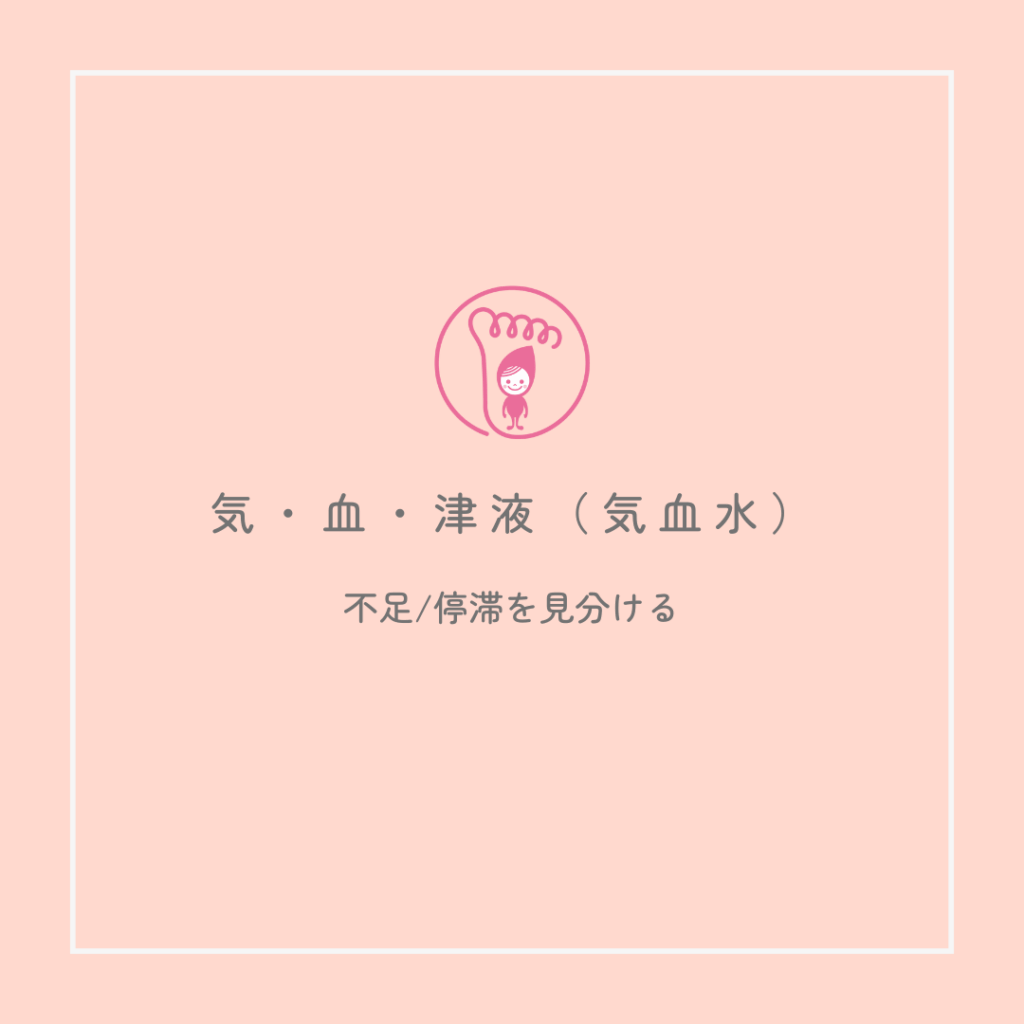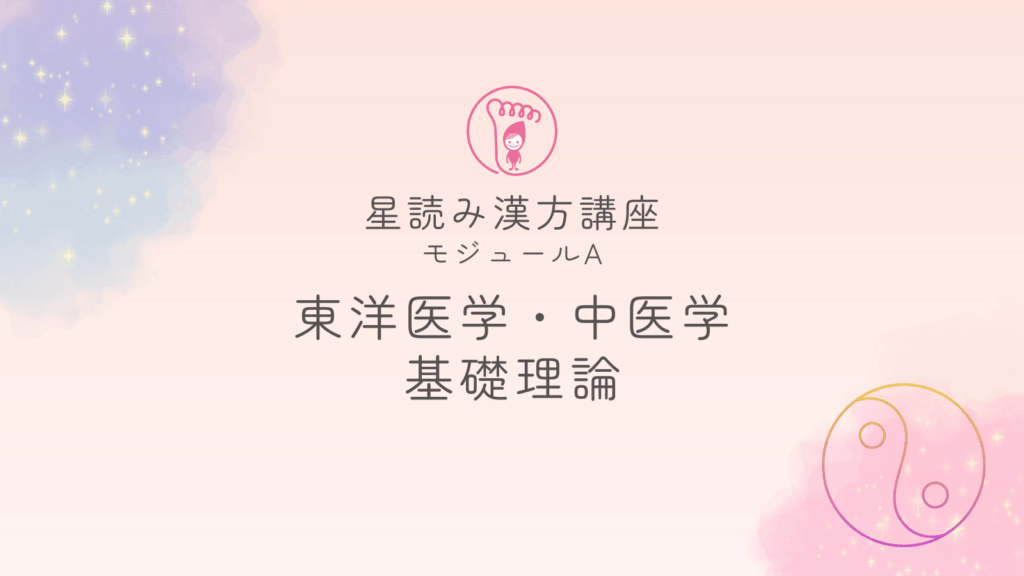
東洋医学・中医学基礎理論
陰陽・五行・気血津液・臓腑・診断学の学びを通して、不調の原因・流れを一筆書きに。
弁証の仮説からセルフケア設計書に繋げる基礎を作ります。
実際に日常生活の場面、自分自身の身体の調子、メンタルの調子を読み解くために必要な「東洋医学・中医学の思考回路」を学ぶ講座です。
できるようになること
●不調を東洋医学・中医学の言葉に翻訳する
日々、身体から感じ取れる不調の訴えを3つの弁証「八網弁証→気血水(津液)弁証→臓腑弁証」で、整理することができるようになります。
●体表に表れた状態を東洋医学・中医学の言葉に翻訳する
身体を診方(中医診断学)を通して、主観だけでなく、客観的な視点「舌の状態・脈の状態・体表(経絡や皮膚の状態)」の情報を元に、弁証の仮設を補強することができるようになります。
●セルフケア設計を作成するための「原因→養生」を一筆書きにする
弁証の仮説を元に、セルフケア設計書を作成するために、原因とその養生方法を会得し、「不調の原因はこれだから、この養生法を自らが自由に選択できる」ようになります。
- 東洋医学を学んだが、普段での生活での生かし方がわからない人
- セラピストや施術者など、カラダの読み解き方など学びたい人
- 相談やカウンセリングの現場で迷子になりやすい人
- 星読みからメンタルの整えだけでなく、身体の整えに生かしていきたい人
- 病気ではないが、いつも何となくの不調を抱えている人
- 自分や家族の不調の原因などを読み解いてみたい人
カリキュラム概要と日程
全8回・3週ごと土曜日 10:00–12:30に開催
受講方法:ZOOM(オンライン)/録画アーカイブ
受講資格:なし(初学者歓迎)
受講費:¥88,000(全8回)|単発:¥13,000/回(各モジュール最大3回まで)|再受講半額
| テーマ | 日程 | |
| A-1 | 陰陽・五行・五臓・五神 概論 | 2026/02/07 |
| A-2 | 気・血・津液(気血水) | 2026/02/28 |
| A-3 | 病因病機と八綱弁証 | 2026/03/21 |
| A-4 | 臓腑①:肝・脾 | 2026/04/11 |
| A-5 | 臓腑②:肺・腎 | 2026/05/02 |
| A-6 | 臓腑③:心・心包・三焦 | 2026/05/23 |
| A-7 | 診断学①:問診・望診 | 2026/07/04 |
| A-8 | 診断学②:経絡×皮膚×足指・反射区 | 2026/04/25 |
到達目標の達成にむけて
各クラスを通して1つの症例を段階的に仕上げる“統合課題(モジュール提出物)”があります。その総合課題を仕上げるために、各クラスごとに課題提出物を準備しています。1クラスずつ、ゆっくりと積み上げていきましょう。
ケーススタディ1件について
- 弁証仮説シート(八綱弁証/気血津液弁証/臓腑弁証をそれぞれ行う)
- セルフケア設計書 ドラフト
- 目標・優先順位
- やること/やめること(昼・夜 各2つ)
- 受診の目安
- デイリーチェックノートの観察項目(睡眠・胃腸・気分 等)
A-2(気血津液):そのケースの気血津液メモ(不足/停滞の根拠)+マップ該当欄の更新
A-3(八綱):八綱弁証メモ(表裏・寒熱・虚実を3パターン試作)
A-4(肝・脾):肝/脾の関与有無をメモ+生活トリガー3つ
A-5(肺・腎):衛気/津液/精の観点から肺/腎の関与有無をメモ
A-6(心・三焦):睡眠・情緒・循環(血・津液)から心/三焦の関与有無をメモ+受診の目安(案)
A-7(診断学①):5分問診で聞くべきことは何か?メモ+舌写真1枚の所見→弁証仮説3点を初めて1枚化
A-8(診断学②):体表(皮膚/経絡/足指)所見を加えて弁証仮説3点を最終調整→
セルフケア設計書ドラフトを完成させる
- 一貫性:八綱→気血津液→臓腑が矛盾しない
- 根拠:問診・舌/脈・体表などの所見を必ず紐づけ
- 実装性:提案が具体でデイリーチェックで測れる
- 安全線:受診の目安が明記されている
※本提出物は学習用の言語化・思考訓練です。医療の診断・治療ではありません。
カリキュラム詳細
よくある質問
すべて日常語訳を配布。録画で何度でも復習可能です。
例写真で段階的に習得していきます。モジュールD:症例別臨床でも繰り返し学んでいきます。
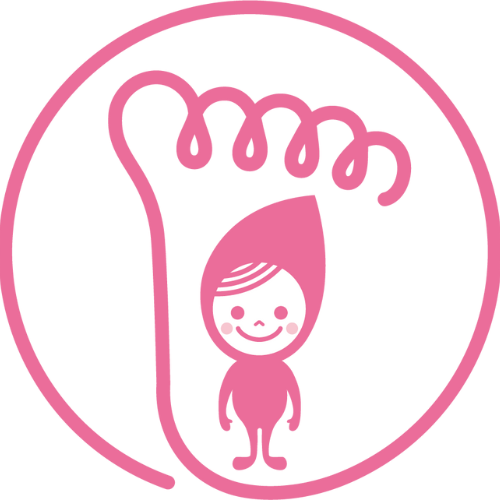 Korognome
Korognome